“質の高い対話”を実現するには?
サントリー様で質問カ・構造化力研修を実施!

株式会社
-
サントリーホールディングス株式会社
コミュニケーションデザイン本部企画部 長坂 翼様
事業部門のよき“カウンターパート”になるために
―本研修実施の背景をお聞かせください。
私たちコミュニケーションデザイン本部には、宣伝部・デザインセンター・お客様志向経営推進部という3つの部署があり、いずれもお客様とのコミュニケーションに関わる役割を担っています。営業のように直接的に売上に貢献する部署ではない中で、私たちが価値を発揮するために必要なのが“カウンターパートカ”です。
サントリーには、ビールや飲料など各種事業部門がありますが、私たちはその事業部門と並走しながら、製品やコミュニケーションの戦略を共に考えるパートナーとして存在しています。例えばビールのような差別化が難しい商材であっても、「サントリーらしい商品」「サントリーらしい広告」とするために、私たちが事業部の“カウンターパート”として関わっています。

そして、この“カウンターパート”としての力を高めるには何が必要かと考えた時にたどり着いたのが、「質問力」と「構造化力」です。
質問力は、私たちの部署ならではの視点で質問を投げかけることで、議論を深めたり、行き詰まりを打開したり、本質的な課題にアプローチするためのカです。そして、構造化力は、意見を端的に伝えること、そして、議論で発散した情報を整理するために重要な力だと考えています。今回の研修は、この2つのスキルを育成することを目的に実施しました。
―弊社にお声がけいただいたきっかけを教えてください。
当時、同じ部署で働いていたメンバーからデルタスタジオさんを紹介されたので、私自身、御社の書籍『世界ーやさしい問題解決の授業』の左脳編・右脳編の両方を読ませていただきました。内容自体が中学生でも理解できる非常にわかりやすいものであること、そして、左脳的なアプローチと右脳的なアプローチを提示している点がとても新鮮で、印象に残りました。
私たちの本部の中には、デザインセンターのように“右脳的な発想”を大切にしている部署もあるので、非常に親和性が高いと感じました。
また、私個人としては一般的なビジネス書に対して「答えはこれです」「このステップを踏みましょう」といった方法論を一方通行型で押し付けられる印象があるのですが、御社の書籍は読み手に考え方の幅を委ねている部分も非常に面白いと感じました。
こうした左脳×右脳のアプローチや柔軟性に魅力を感じ、「ぜひ一度ご一緒してみたい」と思いご依頼させていただきました。
実践型で「質問力」と「構造化力」を学ぶ
―具体的にどのようなプログラムを実施されたのでしょうか?
まずは質問力のプログラムからお話しします。質問力という言葉を聞くと、“質問をたくさんする力”と捉えられがちかもしれません。しかし、今回の研修で私たちが重視したのは、そうした問いの「量」ではなく、議論を活性化し、前に進めるための問いの「質」を高めることでした。そのために、本研修では「反対から考える」「制約を外す」「目的に立ち返る」という3つの質問を取り上げました。
「反対から考える」では、ジョン・F・ケネディがキューバ危機への対応を検討する際に、あえて反対意見を出す“悪魔の代理人役”を設けた事例、「制約を外す」では、インテルの元CEOが「もしも自分たちがクビになって、新しいCEOがきたら何をするだろうか?」という問いによって、経営陣の思考の制約を外した事例など、具体的なエピソードを交えて、非常にわかりやすく解説していただきました。
演習の際に、私も“悪魔の代理人役”としてあえて反対意見を言ってみたのですが、反対意見を言うことや、言われることに意外と慣れていないもので、皆さん新鮮だったようです。
二つ目が構造化力です。今回の研修では、ピラミッドストラクチャーを使って、自分の考えを可視化し、ロジカルに整理したり、広げたりする力を学びました。
質問力も構造化力も、コミュニケーションデザイン本部に限ったスキルではなく、社員の共通言語になったら、もっとレベルアップにつながるという感触を持ちました。
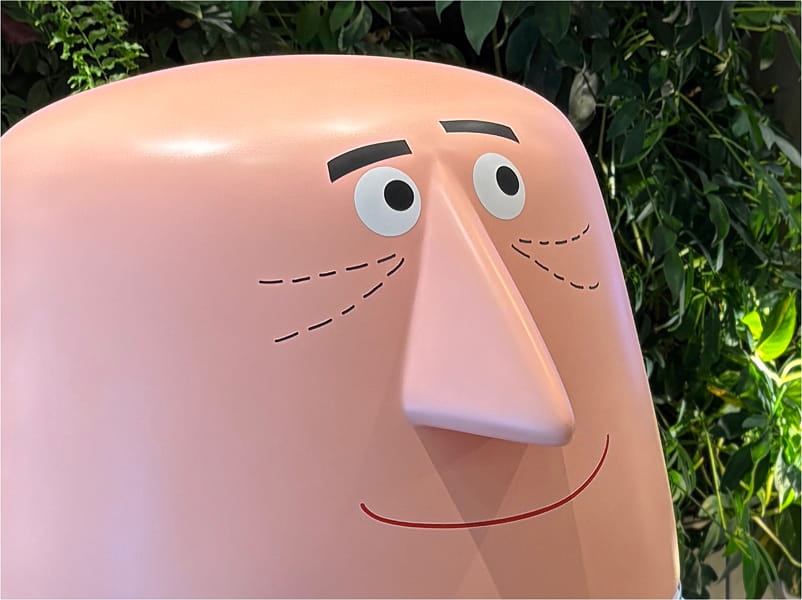
そして、これら2つのスキルを活かした実践演習のパートも非常に印象的でした。
たとえば、ブレストの前に各自で考える時間を設け、さらにその際にはCrazy8(8分と時間を区切って8個のアイデアを強制的に考える手法)を活用することで、他の人のアイデアに影響を受けることなく、多様なアイデアが短時間で出てくることを体感できました。“明日から使える”実践的な内容でした。また、演習の際には一人に「意思決定者」という役割が与えられ、その立場から考えたのですが、選ばれたメンバーは戸惑いながらも真剣に取り組んでいました。
私たちはカウンターパートとして事業部門と対話し、提案を行う立場にあります。その際、「相手はどのように考えているのか」「どんな情報があれば意思決定できるのか」といった視点を持つことは非常に重要です。今回の研修を通じて、そうした感覚を実践的に体験し、磨くことができたと思います。
楽しい!わかりやすい!
部署の壁を越えた実践形式の研修
―受講者の事後アンケートでは高評価で、「お勉強チックにならず、楽しく学べる良い研修だった」「わかりやすく、しかも面白く説明いただき、活発に議論できた!」といったコメントをいただいています。
長坂さんとしての手応えはいかがでしたか?
今回の研修では、受講者側が置いてけぼりにならないように、一方的な講義とならないようにすることを意識し、講義だけでなく実践も交えながら進めていただいたことで、受講者がしっかりと気付きを得られる内容でした。とにかく“わかりやすく、楽しく”学べる研修だったと思います。
受講者からも、「非常にためになりました」というようなコメントばかりで、しっかりと好評をもらえたと、非常に満足しています。
また、コミュニケーションデザイン本部は3つの部署から成り立っていますが、それぞれが専門性を持っているため、そこまで部署間の交流は活発ではありませんでした。
しかし今回の研修では、内容自体はもちろん、ディスカッションや、工夫されたグループ分けを通じて、部署を超えたコミュニケーションが活性化したことが良かったと感じています。
当日、初めましての人同士がグループを組んだ研修だったにも関わらず、いい意味で騒がしい研修になったなと思っています。
―最後に、デルタスタジオと仕事をされてみていかがでしたか?
講師を呼んで学ぶ研修は、私が異動してきてからは、初めての試みでしたが、とにかく柔軟に対応していただけたと感じています。
部署間の交流を活発にする工夫や、本来であれば1日かかる内容を3時間に凝縮するご相談に柔軟に対応いただいた点や、内容の取捨選択について、私たちの要望をしっかりと汲み取りながら臨機応変に対応いただきました。
サントリーでは、新人社員研修でも“体を動かす”、“手を動かす”といった参加型のスタイルを重視しています。そうした意味でも、デルタスタジオさんの研修スタイルには非常に共感できましたし、お願いして本当によかったと感じています。


